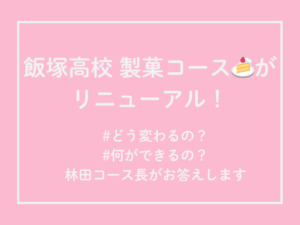生徒が地域イベントを企画運営。飯塚高校「まちLabo」の圧倒的成長と未来——発起人・堀之内翼先生に聞く

飯塚高校では、生徒が主体的に地域と関わるプロジェクト「まちLabo」が2025年6月にスタートしました。地域イベントの企画運営や企業との連携を通じて、実社会で役立つコミュニケーション力や交渉力、逆算思考、行動推進力など、多様なスキルを身につけています。こうした地域活動に取り組んだ経験は、大学の総合型選抜・推薦入試などで大きな強みとなるだけでなく、人間的な成長にも直結します。
今回、本プロジェクトを立ち上げた堀之内翼先生に結成の背景や活動内容、生徒たちの成長の様子、そして「学校内ベンチャー企業」としての将来構想についてお話を伺いました。まちLaboがもたらす一石二鳥以上の学びとその可能性に迫ります。
「街なか学園祭」を起点に深まった地域とのつながり

——最初に、堀之内先生が飯塚高校に着任された経緯やプロフィールを教えてください。
私は2018年に飯塚高校に着任しました。出身は宮崎県、大学は山口大学で、飯塚との直接的なつながりはありませんでしたが、当時の教頭先生が私と同じ高校の出身で、そのご縁から声をかけていただきました。特進コースを担当し、数学を教えています。着任1年目から生徒会顧問を任され、体育祭や学園祭をはじめとする学校行事や部活動応援の企画〜実行に関わるようになりました。
——生徒会顧問歴は7年と伺っています。
最初の1年目は学校側からの指名で始まりました。教員になる前の私は生徒会とはあまり縁がありませんでした。高校時代に生徒会長に誘われたこともありましたが、「学校のために献身的に活動する集まり」というイメージから、自分には向かないと断った思い出があります。
しかし、教員として関わると、生徒たちが学校をより良くしようと懸命に動く姿を間近で見ることができ、その取り組みを支えることにやりがいを感じました。2年目以降は自ら志願して顧問を続け、生徒と一緒に企画を考え、形にしていく日々を2024年度まで送ってきました。
——生徒会の経験がまちLaboにつながる転機は何だったのでしょうか?
2021年7月、創立60周年記念事業として飯塚市商店街連合会・飯塚商工会議所と連携協定を結びました。これにより教育活動と地域活性化を結びつけた本格的な協力体制が始まりました。
以前から製菓コースの販売店「プチフル」出店や、地域行事「山笠」への参加を通じて、地域との交流はありましたが、協定締結後は生徒会を含む多くの生徒が商店街と関わる機会が増えました。
転機となったのは2022年秋の「街なか学園祭」です。先の連携協定を契機に、全国初となる商店街での全校文化祭を実施しました。商店街全体を会場にした2日間の学園祭は前例がなく、話題になった一方で、ゼロから形をつくる難しさもありました。
開催までの準備に全力を注ぐあまり、初日の終了後になって初めて「片付けはどうする?」と慌てて話し合う場面もありました(笑)。ですが、地域の方々と協力してひとつのイベントをつくり上げた達成感は大きく、この経験が地域と学校をつなぐ活動の本格的なスタートとなりました。ここで生まれた商店街とのつながりが「土曜マルシェ」やまちLaboの活動へと発展していきます。
制約の中で伸びる自走力や行動力

——ここからはまちLaboの活動について伺っていきます。6月初旬にまちLaboの結成と活動開始に関するニュースを出しました。改めてまちLabo結成背景と活動内容を教えてください。
まちLaboは、生徒が主体的に地域と関わることを目的としたプロジェクトチームです。6月初旬に結成し、22名の有志が参加しています。主な活動は「土曜マルシェ」の企画運営、産学連携プロジェクト「アーティストレジデンス」、ジュニアアチーブメントとSAPジャパンの共同企画「Social i camp」への参加です。
——初めて仕切った「土曜マルシェ」ではどんな学びを期待しましたか? また、先生はどのような立ち位置でサポートしたのでしょうか。

土曜マルシェを含め、ありがたいことに、地域の方々から本校生徒に対し「手伝ってもらえないか」とお声がけをいただく機会が増えています。
地域からの依頼には必ず背景があります。今回の土曜マルシェでは「来場者減」「運営費不足」という課題がありました。生徒には現状を共有し「限られた予算で人を呼ぶには?」という問いを投げかけました。
こちらが指示を出すのではなく、提示するのはあくまでゴールや制約とし、その達成方法は生徒に考えさせます。SNS活用などの手段を自ら選び、試行錯誤するプロセスこそが主体性と実践力を育てると考えています。
——活動開始から2ヶ月経ちます。生徒たちを見て、どんな変化を感じますか?

募集の時点で「学校外に出て地域と関わる活動をする」ことを明確に伝えていたため、集まったメンバーは最初から意欲が高い生徒ばかりでした。それでも、実際に活動を重ねる中で、主体性の度合いが確実に高まってきています。
特に、役割分担と責任の明確化が功を奏しています。ステージ司会、食品販売、広報など、それぞれに担当者を置き、持ち場を交代制で回すことで、全員があらゆる役割を経験できる仕組みにしました。「誰かがやってくれる」ではなく、「自分がやらないと進まない」状態をつくっています。
また、まちLaboのメンバー全員が集まれるのは週1回、金曜日の1〜1時間半だけです。部活や生徒会と兼務する生徒がほとんどで、所属する各コースもそれぞれ授業や実習があったりと、皆スケジュールが詰まっています。
なので、金曜に週ごとのタスクを決め、顔を合わせない期間はグループチャットで進捗共有を行っています。そうして各自がそれぞれの「宿題」を期日までに進める形です。
——完全にプロジェクト型の進め方ですね。
そうなんです。皆それぞれ忙しいのに加え、学校行事やテストも定期的に入ってくることから、こうしたやり方を徹底しないと、計画通りに進んでいかないという実情があります。7月の土曜マルシェの前もまさにその状況でした。
今年は6月13日に体育祭があり、その時期は私たち教員側が非常に立て込むこともあり、「体育祭が終わってから準備し始めても間に合うだろう」とゆったり構えていたのですが、生徒たちは違いました。「先生、集まりましょう。今のうちに決めて進めたいことがあります」と、逆に提案してきたんです。
体育祭の練習をしていた総合体育館で、練習後に会議室を借りて、急きょ1時間の会議を開きました。進行も彼ら主体で行われます。そこまでしてでも「今決めるべきことは決める」という責任感と、ゴールから逆算して行動する姿勢が彼らにはあります。生徒たちはプロジェクトの全体像を見据えて動いていて、頼もしさを感じています。
学校全体に地域での学びを還元する存在へ

——主体的に考え、動く力が磨かれていますね。地域の大人や企業と関わる機会が多いまちLaboですが、その過程で見られる生徒たちの成長にはどんなものがありますか?
これまでのワークショップや実践の場を通じて、社会に出ても通用する力、たとえば人と話す力、考えを伝える力、相手と交渉する力などが着実に伸びています。
私の感覚では、「会社を立ち上げます」となったときに必要なノウハウが、ある程度身についてきていると感じます。もちろん、すべてが思い通りに進むわけではありませんが、大人を相手に交渉する機会が多く、目上の方との会話の仕方や立ち居振る舞いを、この2ヶ月ほどで確実に吸収してくれています。
広報のための電話のかけ方や名刺交換といったビジネスマナーも指導していますし、配布物ひとつにしても「どうすれば相手に届くか」を生徒自身が深く考えるようになりました。最初は修正をお願いすることも多かったのですが、その回数も着実に減っています。
これは、PDCAを回す中で精度が上がっている証拠です。たとえば「この日までにチラシを作ってね」と伝えても、はじめは期限を守れないことがありました。それでも一度提出してもらい、「ここをこう直そう」とフィードバックをすると、次からの反応が格段に早くなる。そうやって自分の手がけたものが目に見えて良くなっていく実感は、生徒たちにとって大きな誇りになっているはずです。その成長のプロセスを間近で見られることは、私にとっても大きな喜びですね。

——社会に出ても通用する実践的な学びをたくさん得ているんですね。そんなまちLaboのメンバーには、ほかの生徒たちにどんな影響を与える存在になってほしいと考えていますか?
まちLaboのメンバーはさまざまなクラスから集まっています。だからこそ、ここで得た知識や経験をそれぞれのクラスに持ち帰り、周囲に還元してほしいと思っています。
活動が始まって間もないこともあり、「どんなことをしている組織なのだろう」と感じている人もいるかもしれません。地域と関わっていることは理解してもらえていても、まだ生徒会活動の延長のように見えている部分もあるでしょう。
だからこそ、クラスに戻ったときにリーダーシップを発揮し、学園祭などの場で成果を形にできるといいと考えています。最終的には、「このクラスはまちLaboのメンバーが活躍したから売上が伸びた」といった具体的なデータが示せれば、活動の価値はさらに高まり、学校全体への浸透も加速するはずです。
目指すは学校内ベンチャー企業立ち上げ
——今後の展望を教えてください。
まちLaboを学校内ベンチャー企業のような存在に育て、そこで生まれた収益を地域に還元できる仕組みをつくりたいと考えています。飯塚高校は、商店街との強いつながりと私立ならではの自由度という恵まれた環境があるからこそ、こうした活動をさらに広げられると思っています。
実は、まちLaboの立ち上げを準備していた頃から、いずれは学校内ベンチャー企業へという構想は頭にありました。きっかけは、生徒会顧問をしていたときに参加した「高校生自転車ヘルメット着用促進リーダーズグランプリ」です。飯塚高校はモデル校として出場し、その会場で出会った朝倉東高校が、学校内ベンチャー企業 Easter Inc.を立ち上げて活動している姿を見て、とても刺激を受けました。
まちLaboでも、会社を運営するような感覚で組織を動かしていきたいと考えています。現在は「できるだけお金をかけずに」という方針でイベント運営や商品販売を進めていますが、販売による収益も少しずつ増えてきました。最終的には、その利益を生徒に分配するのか、商店街に還元するのかといった選択肢が生まれるでしょう。今のところは商店街への還元を基本方針とし、「100万円貯まったらトイレを1基設置する」といった具体的な目標も描いています。
地域と連携しながら実際のビジネスの流れを学び、その成果を地域に還元する——教育と社会貢献の両輪で走る組織として、まちLaboを成長させていきたいと考えています。
——ワクワクするお話をありがとうございました!
まちLaboは地域と学校をつなぎ、生徒が主体的に動くことで社会で通用する力を育む実践の場です。活動を通じて得た経験や人間力は、大学進学や社会に出たあとにも確かな財産となります。
今後も飯塚高校は教育目標GLI(Global・Local・Individual)の理念を元に、地域と連携しながら生徒一人ひとりの可能性を引き出し、学びを社会へ、そして未来へつなぐ教育を推進していきます。
※記事内容は取材当時(2025年8月)のものです。
▶「まちLabo」について詳しくはこちらを参照ください。