「街なか学園祭から始まった連携が線でつながり、シニアの張り合いと地域の活力をもたらしている」(シルバー人材センター常務理事 山上紀彦さん)
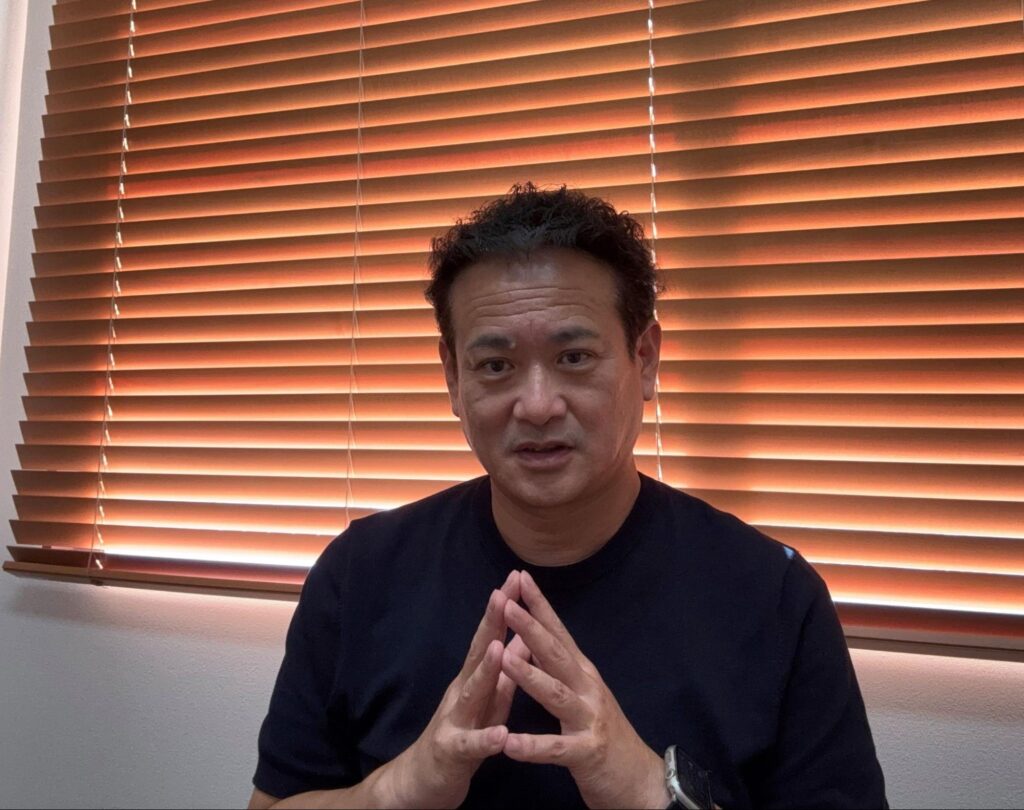
飯塚高校と飯塚市シルバー人材センターの関わりは、2022年の「街なか学園祭」をきっかけに大きく深まりました。以降、両者は地域活動のパートナーとしてともに歩み、産学連携プロジェクト「アーティストレジデンス」や地域活性化を目的とした有志生徒組織「まちLabo」、そして毎年秋恒例となった街なか学園祭など、多彩な場面で連携しています。
シルバー人材センターの会員の方々にとっても、この協働は「若い世代と一緒に活動できる生きがい」そのものであり、口コミを通じて新たな会員が増えるきっかけにもなっています。世代を超えた交流が広がることで、地域全体に活気が生まれ、飯塚のまちづくりに新しい風が吹いています。
ここでは、飯塚市シルバー人材センター 常務理事/事務局長 山上紀彦さんに、これまでの取り組みとそこに込めた思い、そして飯塚高校との連携がもたらす地域の変化について伺いました。
「街なか学園祭」きっかけで交流が深まった

――まずは、山上さんの現在の役職や飯塚とのつながりについて教えてください。
私は2022年9月に飯塚市シルバー人材センターの常務理事に就任しました。もともと飯塚市の出身で、18歳まで地元で過ごしました。現在は福岡市を拠点にしていますが、毎日1時間半かけて飯塚まで通っています。
シルバー人材センターの上部団体に所属していたご縁もあり、故郷である飯塚に貢献したいという思いから、この地での活動に関わるようになりました。生まれ育った地域だからこそ、シニアの力を生かして新しい可能性を広げたいと強く感じています。
飯塚とのつながりを語るうえで欠かせないのが、祖父の存在です。祖父は飯塚の「嘉穂劇場」を運営していました。嘉穂劇場は昭和6年(1931年)に開場した、江戸時代の歌舞伎様式を伝える木造2階建ての芝居小屋です。
石炭産業の発展とともに地域の人々に愛されてきた劇場で、筑豊の人々の文化と娯楽を支えてきました。炭鉱の衰退や災害を乗り越え、遠賀川流域にかつて48座あった芝居小屋の中で唯一残った存在でもあります。
嘉穂劇場は私にとっても「地域の文化を支える」という価値観の原点でした。令和3年(2021年)に市へ無償譲渡され、現在は改修や新たな活用に向けた取り組みが進められています。幼い頃から地域文化やまちづくりに触れてきた経験が、今の私の活動にもつながっていて、飯塚市で地域に根ざした取り組みを進めることは、自然な流れだと思っています。
――飯塚高校との関わりは、いつから始まったのでしょうか。

嶋田学園の嶋田吉勝理事長に嘉穂劇場の理事を務めていただいていたご縁はありました。ただ、高校との本格的な関わりは、私が就任した直後に始まった「街なか学園祭」からです。
事務局長に就任した9月、ある先生がシルバー人材センターの事務所を訪ねられ、「本町商店街で学園祭を行うので協力していただけませんか」と依頼をいただきました。第一印象は「すごいことをされるな」という驚きでした。聞いたことのない新しい試みでしたが、同時に閑散とした商店街が人で溢れかえる光景が頭に浮かび、「もしそれが実現できるなら、できることはすべてやりたい」と強く思い、すぐに協力を決めました。
初年度は、シルバー人材センターが運営する店舗で生徒と一緒に「たこせん屋」を出店し、「海老せんべい」と「たこ」を組み合わせた「たこせん」を販売しました。高校生の明るい姿と地域の方々の笑顔が重なり、「これはすごい取り組みになる」と確信したことを今でも覚えています。
【関連記事】サッカー部×シルバー人材センターのコラボ【飯塚高校のLocalな取り組み】
――当時コラボ出店したのは健康スポーツコースのクラスで、サッカー部の生徒も多く所属していましたよね。

そうなんです。そのご縁から、のちにはシルバー人材センターの会員がサッカー部のホーム試合に応援に駆けつけたり、食事会を開いたりといった交流も生まれました。学園祭をきっかけに、部活動や日常の場面へと交流が広がっていく流れができたのは、とてもうれしいことでしたね。
高校生と地域の人々に育まれる深い交流
――2022年は創立60周年記念の意味合いも強かった街なか学園祭ですが、その後も毎年続き、今では飯塚高校を代表するイベントとなっています。2023年、2024年と、シルバー人材センターと飯塚高校の間ではどのようなコラボレーションが生まれたのでしょうか。
2023年には、販売だけでなく防災アプリの使い方を高校生がシニアに教えるブースを設けました。震災をきっかけに私たちが取り組んでいた「スマートフォンを使った避難情報や災害対策アプリの活用」を、高校生がシニア世代にレクチャーするという試みです。販売ブースと合わせて、2クラスほどを受け入れたと記憶しています。
2022年の経験があったからこそ、「シルバーとしてはこういうお手伝いができますよ」と、こちらからも積極的に提案できるようになり、準備段階からより明確なイメージを持って臨めました。また、前年に参加したシルバー会員から「楽しかったよ」という声が広がり、仲間がさらに増えていったことも大きな変化でした。
私たちは基本的にサポート役に回る立場でしたが、高校生たちが生き生きと活動する姿を間近で見られたことは、シニアにとって大きな張り合いになったようです。まさに「高齢者の生きがいづくり」の一環にもなり、第2回目となるこの年は、私たち自身もより楽しみに臨むことができました。

そして2024年には、古民家カフェ「とまり木(※)」を9月にオープンし、そのすぐ後の11月に街なか学園祭を迎えました。新しい拠点を持ったことで、前年までの店舗出店にとどまらず、テーブルや機材の貸し出し、ガスボンベの手配・搬入など、イベント運営全体を支える役割を担うようになったのが特徴です。
※2024年9月にシルバー人材センター会員が、グッデイの資材や道具を使ってDIYで施設を改装。日曜大工程度の経験者から元大工や職人まで幅広い人が参加し、プロの技と素人の工夫が融合した手づくり感のある再生を実現。現地を訪れたグッデイ柳瀬社長や嶋田常務理事からも感動するほど、素晴らしい空間に。試験的な空き店舗再生としても成功し、今後はプロジェクトとして横展開も予定されている。
シニアのマンパワーを生かし、必要とされる場面に幅広く関わることで、会全体を下支えする存在となっていきました。この年は関わるシルバー会員もさらに増え、活動規模が一層拡大していったと感じています。
――これまで3年間関わってこられて、街なか学園祭が商店街や地域にどんな変化をもたらしてきたと感じられますか。また、飯塚高校の生徒たちの姿にはどんな成長や変化を見てこられましたか。
3年間関わってきて一番強く感じるのは、回を重ねるごとに確実に盛り上がりが大きくなっているということです。来場者数も明らかに増えており、当初は商店街の中だけで完結していたものが、今では周辺エリアにまで広がり、お祭りの雰囲気がどんどん膨らんでいくのを実感しています。
受け入れる側にとっても、初年度は手探りで戸惑うことが多かったのですが、経験を重ねるにつれて要領がつかめ、生徒さんたちとの距離も徐々に縮まっていきました。3年目には、準備や運営の場面でも自然にコミュニケーションが取れるようになり、日常でも「とまり木」の前を通る生徒が笑顔で挨拶してくれるなど、普段の関係性にも広がりが見えてきています。
学園祭をきっかけに、商店街全体が活気づくだけでなく、高校生と地域の人々の間に新しい交流の芽が育ち、それが地域全体の賑わいにもつながっているのだと強く感じています。
――2025年の街なか学園祭について、シルバー人材センターとしてはどのような取り組みを予定されていますか。新しい挑戦もあれば伺いたいです。
今年(2025年)については、まだ詳細が固まっていない部分もありますが、すでに委員会の打ち合わせに参加し、シルバー人材センターとしての関わり方を模索しています。
これまでの3年間は、私どもとして「第一章」と位置づけています。嶋田吉朗常務理事とも振り返りをしましたが、大きな課題もなく、むしろ順調に積み重ねてこられたと感じています。だからこそ、ここからは「第二章」として、さらに集客力を高めていくステージに進むべきだと考えました。その一環として、外部のエンターテインメント企業に協力をお願いしてはどうかと、私から提案をしたんです。
また、シルバー人材センターが商店街の理事に加わり、今年からは「商店街の運営側」という新たな立場になったことも大きな変化です。外国人の受け入れやアート関連、とまり木の立ち上げなど多岐にわたる活動が評価され、商店街から打診を受けて就任に至りました。学園祭が商店街にとって一大イベントであることを、初回から関わってきた私たちはよく理解していますので、今年はその役割をより強く担いたいと思っています。
具体的には、これまで通り2店舗を活用して生徒と一緒に出店しながら、さらに商店街全体の盛り上げにも力を注ぎます。そして今年は特に吉本興業さんのご協力をいただき、芸人さんを招いてエンターテインメントの要素を加える計画です。従来の出店に加え、全体を見渡す立場から祭りをさらに盛り上げていく――これこそが、2025年に挑む「第二章」の姿だと考えています。
点で終わらない。「線で続く活動」を目指して
――これまで3回学園祭に関わってこられて、当日の盛り上がりはもちろんですが、その熱気が日常や商店街にどう広がっているのかも気になります。山上さんから見て、学園祭の活動が年間を通じてどのようにつながっていると感じられますか。
学園祭当日だけでなく、準備や片付けもともに行うことで、より深い協力関係が築かれています。大切なのは、この活動を「点」で終わらせず「線」としてつなげていくことです。これは常務理事ともよく話すのですが、学園祭を単発のイベントにせず、年間を通じて地域と学校が関わり続けることこそが本当の町おこしだと思います。
実際、2025年7月からまちLaboに企画・運営をしてもらうようになった土曜マルシェ、産学連携プロジェクト「アーティストレジデンス」のワークショップなどの取り組みが定着しつつあり、週1回あるいは隔週といった高い頻度で商店街での活動が続いています。
こうした積み重ねが、11月の学園祭という「総決算」につながっているんです。打ち上げ花火のように一度きりで終わるのではなく、1年間の流れの中に学園祭が位置づけられることで、生徒にも地域にも大きな意味を持つようになっていると感じています。
――今、山上さんのお話の中でまちLaboという言葉が出ましたが、彼らとシルバー人材センターも深く連携していますよね。実際にまちLaboの生徒たちとどのような交流があり、山上さんご自身はそれをどう感じていますか。

まちLaboの生徒さんたちとは、土曜マルシェやワークショップを通じて最も頻繁に交流しています。土曜マルシェでは、私たちが店舗をお貸ししたり必要な機材を準備したりして、一緒に運営を行っています。そこにはシルバー会員も加わり、生徒と地域の方々が自然に交わる場面が日常的に生まれています。
私の目には、まちLaboの活動は「学園祭のミニバージョン」として映ります。こうした取り組みでの経験が11月の本番につながっており、準備段階から地域と関わる仕組みが定着していることに大きな価値を感じます。
特に印象的なのは、生徒たちが地域に根ざしながら新しい発見や提案を積極的に行う姿です。常設の組織としてまちLaboがあることで、商店街と学校を結ぶ風通しの良いパイプができ、将来への明るい可能性が広がっていると感じています。
実際に、シルバー会員と生徒が一緒に活動する姿を見た地域の方から「とてもよい取り組みですね」と声をいただくこともあります。その姿に触発され、新たに会員になりたいと希望される方も出てきています。学校・シルバー人材センター・商店街が相乗効果を生み出している――まさにそんな実感を得ています。
飯塚高校との連携はシニアに生きがいをもたらしている

――これまで学園祭やまちLaboを通じて、高校生と地域、そしてシルバー人材センターの皆さんとの関わりが深まってきたことを伺いました。実際にそうした取り組みが会員さんの気持ちや活動、さらには新規入会にもプラスの影響を与えているのではないかと思います。
その通りで、飯塚市シルバー人材センターは、実は福岡県下でも特に伸び率が高いんです。人口規模では福岡市や北九州市の方が大きいですが、入会率で見ると昨年度は飯塚市が県内トップでした。これは大きな特徴だと思います。
世代間交流は一過性で終わることも多いのですが、飯塚高校との取り組みは今年で4年目を迎え、継続的に続いています。シニアにとっては社会に関わり続ける張り合いとなり、高校生にとっては地域で実践的に学ぶ場となる。互いに刺激を受けながら協力することで、イベント運営を超えた「地域の共創」が生まれていると感じています。
シニア世代が外に出やすく、自分の経験や力を発揮できる環境をつくることが私たちの役割ですが、この連携はまさにその好例です。「関わらなければ家に閉じこもっていたかもしれない」「若い世代と一緒に活動できるのが楽しい」といった声も多く寄せられています。高校生とともに地域を盛り上げることは、世代を超えた大きな財産だと感じています。
――これまで飯塚高校との連携を通じて、シニアの方々が生き生きと活動される様子を伺いました。そうした取り組みは、高齢者の生きがいだけでなく、地域文化の継承や新しい交流の場づくりにもつながっていると思います。そのほかにシルバー人材センターとして展開されている活動を教えてください。
とまり木で、地元の老舗が提供していた「永楽ぜんざい」を復活させたことも大きな話題になりました。この取り組みはさらに広がりを見せ、飯塚高校の生徒とコラボする形で大阪・関西万博 フランスパビリオンへの出店(2025年8月)にもつながったんです。シニアの力で地域の文化を再び輝かせ、世界に発信することができたというのは、非常に意義深い出来事でした。
【関連記事】飯塚高校が大阪・関西万博に出展【産官学民連携「永楽あんぱん」プロジェクト】
まちLaboの皆さんとコラボしているアーティストレジデンスも、シルバー会員がアーティストの制作を支える中で、会員自身が新しい興味を見つけたり、まるで「推し活」のように応援を楽しんだりする姿が見られるようになりました。

たとえば、日本画家の海野良太さんがとまり木の壁一面に大作を描いてくださったときはNHKの取材も入り、女性会員さんたちが一生懸命お化粧をして取材に臨む場面もありました。それを目の前で見ることができ、さらには海野さんに「一緒に写真を撮ってください!」と盛り上がる。まるで少女に戻ったかのように無邪気に喜ばれているシニアの方々の姿を見て、本当に幸せな光景だと感じました。
【関連記事】【産学官連携 商店街アーティストレジデンスプロジェクト#2】海野良太さんとオリジナルTシャツを製作
――ここまで伺っていると、シルバー人材センターのさまざまな活動の中でも、飯塚高校との取り組みはシニアの方々に生きがいや張り合いをもたらし、地域全体を明るく盛り上げる大きな力になっているのだと感じます。まさに世代を超えたつながりが、新しい地域の姿を形づくる一助になっているように思います。最後に、こうした活動をともにしてきた飯塚高校や地域の皆さんへ、山上さんからメッセージをお願いします。
飯塚高校は、公立高校では難しいような新しい挑戦を次々と実現しています。学園祭やまちLaboなど、常に前向きで創造的な姿勢に触れることで、私たちも大きな刺激を受けています。
これからも、シルバー人材センターは飯塚高校と共に新しいことに挑戦し続け、地域を盛り上げていきたいと思います。地域の皆さんにも、学園祭やイベントを見に行くだけでなく一緒に楽しむ気持ちで参加していただけるとうれしいです。
(完)
2022年の街なか学園祭をきっかけに始まった飯塚高校と飯塚市シルバー人材センターの協働は、一イベントの枠を超え、地域を支える新しい力へと育ってきました。
学園祭やまちLabo、アーティストレジデンスなど、多彩な取り組みを通じて、高校生とシニアが互いに刺激を与え合いながら、世代を超えた交流を築いています。その連携はシニアに生きがいをもたらすと同時に、若い世代にとっても実践的な学びの場となり、地域全体の活気へとつながっています。
第二章を迎える街なか学園祭とともに、飯塚高校とシルバー人材センターの挑戦はこれからも進化を続け、地域に新たな価値と可能性を生み出していくことでしょう。


