「英語好きな全生徒に扉は開かれている。“留学したい”を全力でサポートします」(飯塚高校 英語科教員 本晋)
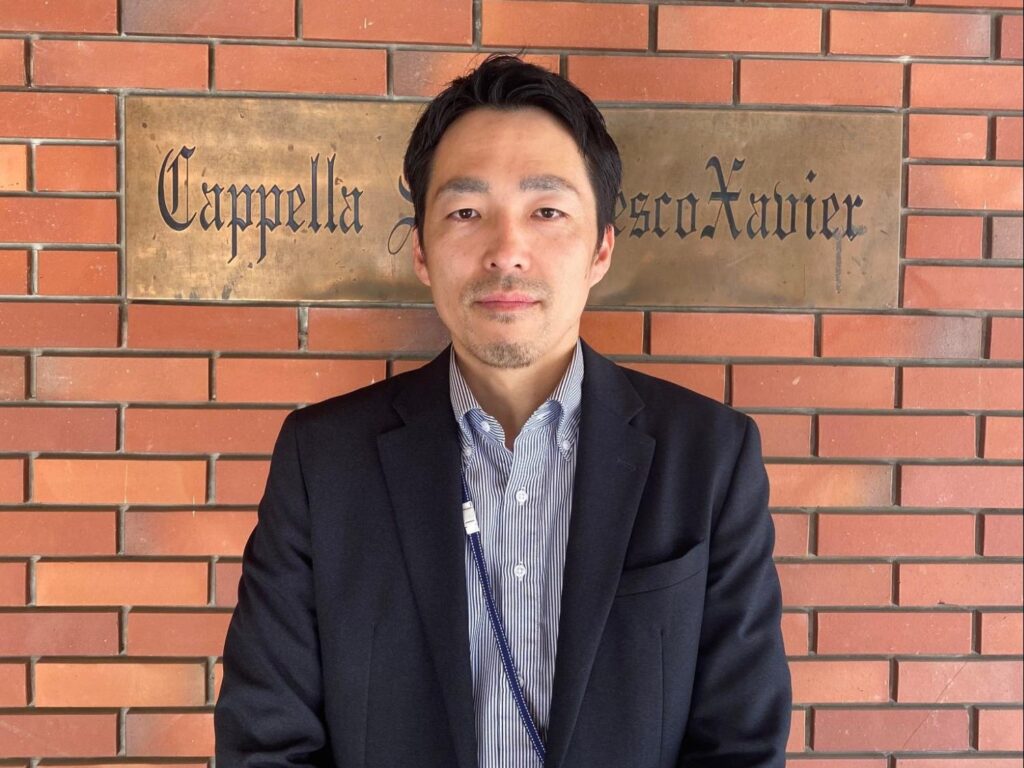
飯塚高校では、生徒一人ひとりの希望に応じた留学を実現するため、交換留学プログラム(以下、留学プログラム)において充実した支援体制を整えています。協定校の拡充や、金銭的負担を抑えた制度設計にも取り組み、国内外での実践的な学びをより身近なものとする工夫を重ねてきました。
今回は、留学支援に携わる教員へのインタビューを通じて、飯塚高校ならではの留学の魅力をご紹介します。
登場するのは、英語科の教員であり、特進グローバルコースの担任、そして交換留学やアジア派遣プログラムの運営を担当している本晋(もと・しん)先生です。
本先生はオーストラリアの大学を卒業後、シンガポール系IT企業の日本法人に勤務。その後、自身の留学経験とグローバルな社会人経験を次世代に生かしたいとの想いから教職へ転身し、2022年に飯塚高校へ着任し、現在はグローバル教育推進室長、グローバル研究部 部長も務めています。
現在は、生徒たちに世界が広がる喜びや異文化交流の豊かさを伝えながら、留学という挑戦を後押ししています。
***
「交換留学プログラムでは、送り出し前の準備から、現地での受け入れ体制づくり、滞在中のサポートまで、すべての段階に関わっています。受け入れの際には、どの授業に入ってもらうかをプランニングしたり、歓迎会やお別れ会を企画したり。生徒本人や保護者からの相談にも丁寧に対応し、安心して過ごしてもらえるようチームで支えています。
一方、送り出しの際は、生徒たちが現地でスムーズに生活できるよう、空港での出迎えからホームステイ先・学校までの移動に至るまで、ドア・ツー・ドアで安全に動ける体制を整えています。現地の学校やホストファミリーとも密に連携を取り、入念な準備を行っているので、留学中に生徒から連絡が来ることはほとんどありません。

飯塚高校には国際入試で入学した生徒や中国からの長期留学生、ネイティブの先生も多く在籍しています。また、グローバル教育プログラムIntensive(グローバル研究部)の活動や本校独自の英語専門授業・IE(Integrated English)の受講などでも、スピーキング・リスニング・リーディング・ライティングの4技能を総合的に鍛えています。こうした環境で過ごす中で、海外を身近に感じている生徒が多く、現地での暮らしに溶け込みやすいのではないかと思っています。

留学を担当してきた中で、印象的なエピソードはたくさんありますが、例えば、あるおとなしい生徒がタイのIBSに留学した際、別人のようにいきいきと自分を表現していたんです。お別れ会のステージで歌ったり、踊ったり。日本の教室では見せなかった姿は、まさに“自分の殻を破った”瞬間でした。
帰国後も『次は〜〜へ行きたい』と留学へのさらなる意欲を見せ、英語を使うことにも積極的に。ネイティブの先生や留学生との交流にも前向きになりました。
一度、海外に身を置き『こういう世界があるんだ』と実感することが、生徒の大きな成長につながっていると感じます。
私は英語科の教員として、特進コースだけでなく、保育や医療福祉など他コースの授業も担当しています。その中で『交換留学はすべてのコース、生徒に開かれている』『英語が好き、海外に興味がある、それだけで十分チャンスはある』ということを、生徒たちに伝えています。
実際、今年度のアジア派遣プログラムでは、特進以外のコースからもエントリー希望者が出てきました。まだ実現には至らなかったものの、“挑戦したい”という気持ちが生まれたこと自体が、大きな一歩だと思っています。
難関大学を目指す特進の生徒に対しては『留学経験は総合型選抜の面接で話せるテーマになるよ』と伝えることがあります。“楽しい”で終わるのではなく、進路にもつながる、“未来をつくる経験”として留学を捉えてほしいんです。
最後に、本校では少ない金銭的負担で交換留学が可能な仕組みを整えていることにも触れておきます。2024年度の実績でいうと、韓国は5万円ほど、タイは13万円ほど、ニュージーランドは27万円ほどと、ほぼ渡航費用のみで行けます。これだけ費用を抑えられるのは、協定校としての取り決めにより、現地の授業料やホームステイ費用がかからないようなプログラム設計にしているからです。そのため現地での留学中はほとんどお金はかかりませんし、受け入れ時は留学生ひとり分の食事やアクティビティなどの実費がかかる程度です。
留学に少しでも興味があるなら、ぜひ挑戦してみてください。飯塚高校にはその想いを後押しし、現実化できる環境があります。一歩踏み出すことで、自分でも知らなかった新しい自分に出会えるはずです」
※記事内容は取材当時(2025年5月)のものです。


