【卒業生インタビュー】九州工業大学大学院修了・キーサイト・テクノロジー所属 蜷川渉さん(2018年3月卒業)
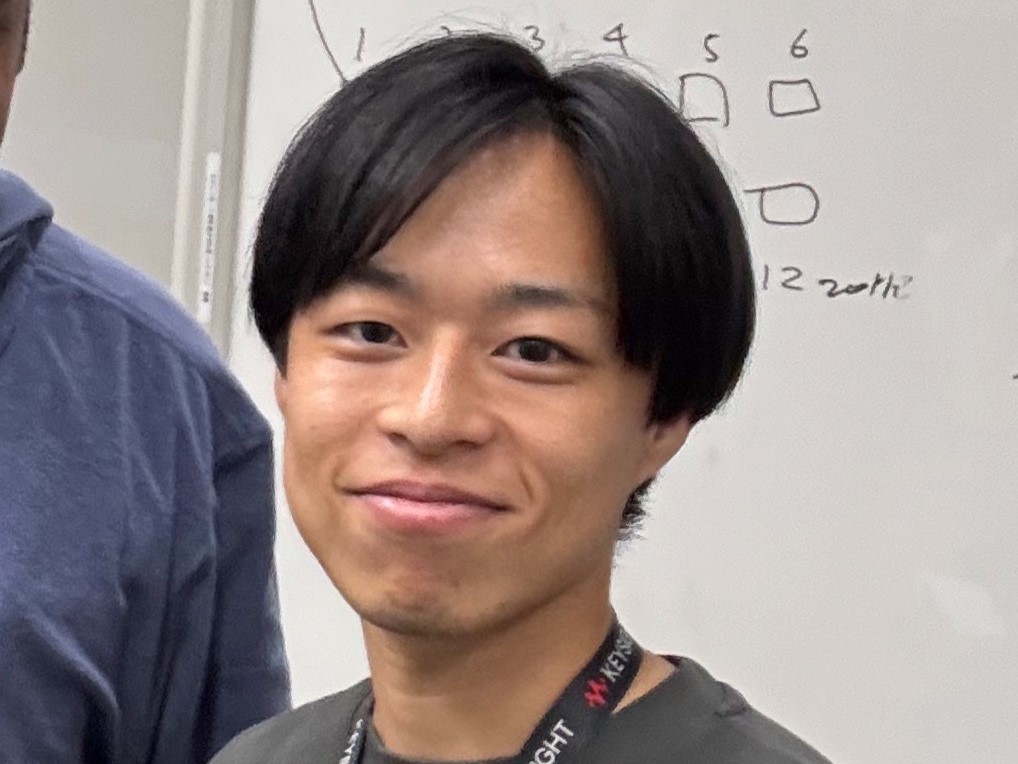
飯塚高校を卒業後、九州工業大学情報工学部、さらに同大学大学院 情報工学府へと進学し、2025年4月からは外資系企業キーサイト・テクノロジーに勤める蜷川渉さん。
高校時代は中辻喜敬監督体制の1期生としてサッカー部に所属し、大学ではフットサル部副部長として活動してきました。
大学・大学院で研究に没頭し、挑戦を重ねた経験は、社会人となった今も大きな糧になっているといいます。蜷川さんに研究や仕事、そして高校時代を振り返っての想いを伺いました。
「見えないものをつくる」奥深さに夢中になった大学時代
——大学ではどんな分野を学んでいましたか?
九州工業大学 情報工学部 知的システム工学科の先進機械コースに所属し、マイクロ/ナノ技術や3Dデザインを基盤とする機械・情報工学を幅広く学びました。その中で、3DプリンターやCADを用いて設計した構造物を制御する研究に取り組み、MEMS(微小電気機械システム)と呼ばれる数ナノ、数マイクロの世界の微小電気機械システムを扱っていました。
——研究の面白さはどんなところにありましたか?
「肉眼では見えないものを形にする」という難しさと奥深さです。何もないところから構造物を設計し、顕微鏡で確認しながら性能を評価していく過程を通じて、目には見えない研究が現実社会につながる手応えを感じました。自分の手でゼロからつくったものが、将来、携帯電話などの内部で使われるかもしれないと思うと、とてもワクワクしました。

——大学生活全般についても伺っていきます。部活動にも熱心に取り組まれていたそうですね。
フットサル部に所属し、副キャプテンとして活動していました。学生主体で運営する部だったので、練習計画から試合運営まで自分たちで決めていく必要がありました。
1・2年の頃、コロナ禍の影響もあって、先輩たちがほとんどいなくなり、部の存続が危うくなった時期がありました。どうすれば活動を続けられるか、どうすれば強くなれるかを後輩たちと話し合いながら取り組みました。結果的に新しいメンバーも増え、今では大きな部に成長しています。

部の雰囲気づくりや運営の仕方は、飯塚高校サッカー部での経験が大きく生きていました。高校時代はチームビルディングに関わる役割を担っていたこともあり、仲間との関わり方や組織としてのまとまり方を学びました。その経験があったからこそ、大学では周りを冷静に見ながら、仲間が楽しめる環境をつくることができたと思います。
自発的に学ぶ姿勢を身につけた大学院時代

——ここからは大学院に関するお話を伺っていきます。大学院に進学された背景を教えてください。
大学3年の頃、就職も考えましたが、ようやく専門分野の入口に立ったばかりで、企業で通用する実力をつけるにはまだ力不足だと感じていました。大学4年から始まる研究活動では、実際に企業でも応用される技術に触れる機会が増えます。
研究をもう少し深めて専門性を高め、会社に貢献できる実力をつけたいと思ったのが進学を決めた一番の理由です。せっかく大学まで来たのだから、その先にある学びを経験したいという気持ちもありました。
——結果的に、大学院に進学してよかったですか?
よかったです。大学院では研究に没頭しながら、後輩への指導をする機会もありました。大学院では、2年生が1年生を教える仕組みになっていて、教える側の立場を経験することになります。「人に教えるためにより深く理解する」経験を通じて、自ら課題を見つけ解決する力を磨きました。
大学院の2年間で「自発的に学び、自ら動く力」を身につけられたことが、今の仕事にも大きく生きています。
「一番チャレンジングな仕事をしたい」外資系企業へ就職
——2025年3月に大学院を卒業後、就職されました。現在のお仕事について教えてください。
キーサイト・テクノロジーの日本法人で、半導体計測装置のマーケティングを担当しています。米国シリコンバレー発祥のヒューレット・パッカード(HP)から分社して生まれた会社で、電子計測装置の分野で高い技術を持つグローバル企業です。
私が所属するのは、半導体パラメータアナライザと呼ばれる半導体計測装置を扱う専門部署になります。職種はマーケティングエンジニアといって、一般消費者向けのマーケティングとは異なり、理系の知識を生かしてお客様の「こういう測定をしたい」というニーズに対し、最適な測定ソリューションを提案する仕事です。営業や開発チームと密に連携しながら、お客様と社内をつなぐ技術の翻訳者・コンサルタントのような役割を担っています。
たとえば、装置の不具合対応や設定変更が必要な際には、海外のエンジニアと英語でやりとりしながら、現地スタッフに対してトレーニングを行うこともあります。技術を理解し、正確に伝える力が求められる点では、大学院での研究や後輩指導の経験が大きく生きています。理系の専門知識をベースに、ものづくりとビジネスを橋渡しする、やりがいのある仕事だと感じています。
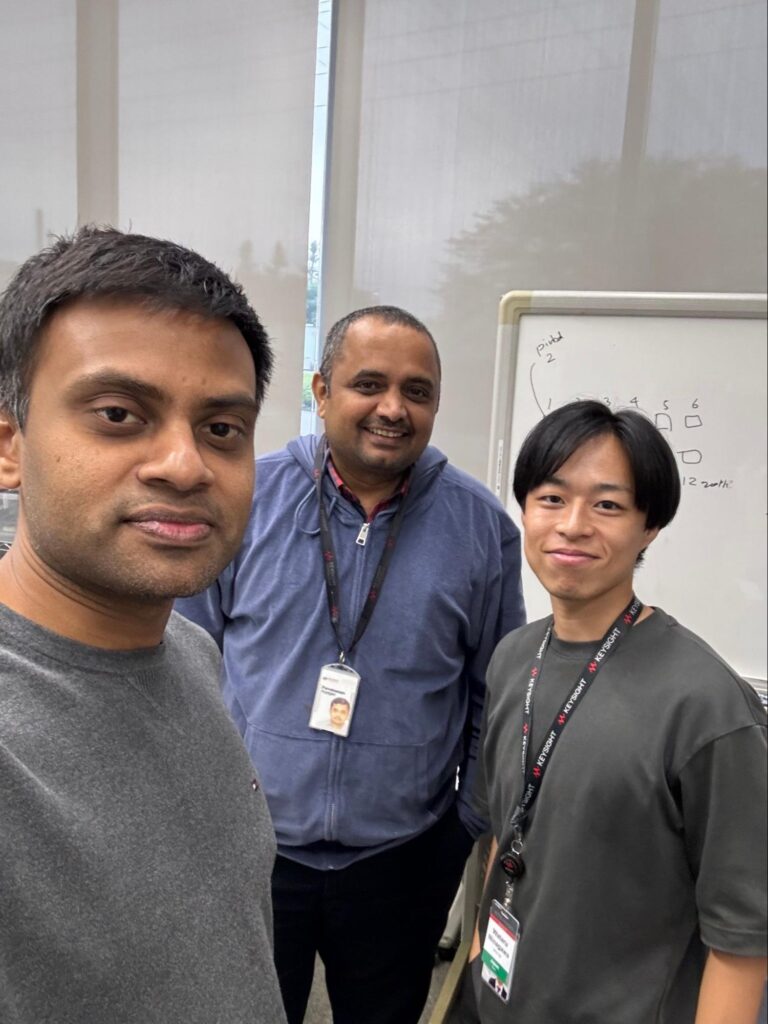
——数ある企業の中でキーサイト・テクノロジーを選んだ理由は何だったのですか。
「最もチャレンジングだ」と感じて心が動いたからです。理系科目が得意な一方、英語は一番苦手な科目でした。だからこそ英語を当たり前に使う外資系企業に入るのは、自分にとって大きな挑戦でしたが、それだけに学べることも成長できることもたくさんあると感じたんです。
インターンシップを通じて、社員の雰囲気や働きやすさ、ホワイトな環境を実際に感じ、「ここなら挑戦しながら成長できる」と確信したことも関係しています。
——挑戦を恐れず進む姿勢はどこで培われたと思いますか?
飯塚高校時代の挫折経験が原点です。飯塚高校に入学した第一目的は「サッカーをすること」でしたが、最後の試合には選ばれず、応援をしていました。サッカーにすべてを賭けてきたつもりだったのに、舞台に立てなかった。そんな現実が本当に苦しく、当時は勉強も手につかなくなったほどでした。
努力しても結果につながらない日々は苦しかったですが、その経験があったからこそ、今ではどんな困難も乗り越えられますし、「苦手を理由に避けるのではなく、あえて挑戦する」自分がいるのだと思います。それから今に至るまで、いろいろな挑戦をしてきたので、今は「一歩踏み出せば自分ならできる」という自信もついています。
苦しかった高校時代が、今の自分の礎に

——この流れで飯塚高校時代を振り返っていただきます。特進コース×サッカー部という多忙な3年間で、どんな学びがありましたか?
大きくふたつのことを学びました。ひとつは「人をまとめることの難しさ」です。どんな組織やチームも同じですが、組織にはいろいろなタイプの人が集まっています。
当時のサッカー部にも個性的な仲間が多い中、「どうすればチームをひとつにできるだろうか?」と日々試行錯誤しながら、仲間との関わり方を模索していました。思い通りにいかないことも多かったですが、価値観の違う人とどう向き合うかを学べたのは、今となっては大きな財産です。
もうひとつは「努力した人には勝てないと知ったこと」です。中辻監督体制になったばかりだったこともあり、チームはレベルが高いとはいえず、弱い状態からのスタートでした。けれど、日々の練習の中で仲間が驚くほど成長していく姿を何度も目の当たりにしました。
彼らの努力を間近で見て、「何がそこまで突き動かすのか」と心が揺さぶられたのを覚えています。その姿を見て、自分ももっと頑張らなければと思う一方で、「本気で努力をする人には敵わない」という現実も知りました。このふたつの学びは自分の原点ともいえますし、今の仕事や生き方の土台になっています。
——学習面についても伺いたいです。印象に残っている先生はいますか。
特進クラスのとある先生が、遅い時間まで残って数学を教えてくださいました。先生のおかげで基礎を十分に身につけることができたので、数学は得意科目といえるほどになりましたし、入試でも苦労しませんでした。親身になってサポートしてくださることが本当に心の支えになりました。助けを求めたら何倍にもして返してくれる先生に恵まれていたと思います。
——最後に、飯塚高校に通って良かったと思うことを教えてください。
一番は、同じ目標に向かって本気で努力する仲間と出会えたことです。全国から集まった仲間たちと寮で過ごした3年間は、今でも私の原動力になっています。飯塚高校サッカー部でなければ、あの経験は得られなかったはずです。
もうひとつは、中辻監督との出会いです。監督は当時、「今の飯塚高校サッカー部は無名。だから、ここに来た。そんな部活を強くして、有名にすることができたら、それはすごいことだ」と語っていました。その言葉を聞き、自分たちの力で現実を変えていけるという自信が芽生えました。
また、部活でうまくいかないことが苦しいあまり退部を考えたとき、夜遅く迎えに来てくださった監督から「今の行動を恥ずかしく思えよ」と言われました。その言葉が心に刺さり、「自分に恥じない行動をする」ことが私の人生の軸になりました。
飯塚高校で出会った仲間と先生方、そしてあの環境が、今の私をつくってくれたと思います。あの3年間があったからこそ、どんな挑戦にも臆せず踏み出せる自分でいられます。
——素敵なお話をありがとうございました!
今後も合格者インタビューを不定期で掲載していきますので、どうぞお楽しみに。
※記事内容は取材当時(2025年10月)のものです。
※コース名などは在学当時のものです。
※大学生活・留学生活に関する写真は蜷川さんよりご提供いただきました。
▶「探究プロジェクト(特進コース)」について詳しくはこちらを参照ください。


