【卒業生インタビュー】シェフィールド大学大学院 教育学修士課程 山本貴子さん(2020年3月卒業)

飯塚高校を卒業後、久留米大学文学部国際文化学科(英語コミュニケーション専攻)へ進学した山本貴子さん。学部在学中には英語の中学校・高等学校教諭一種免許状(教員免許)を取得し、イギリス・プレストンにあるセントラル・ランカシャー大学(UCLan)に1年間の交換留学を経験するなど、密度の高い4年間を過ごしました。
そして2025年9月から、イギリスの名門大として知られるシェフィールド大学大学院の教育学修士課程に進学。グローバルな環境の中で、日本の英語教育のあり方を見つめ直し、教育の本質を追究しています。
山本さんに大学・大学院での学び、そして飯塚高校時代の経験についてお話を伺いました。
大学で学んだ英語教育の基礎と、教職課程で見えた課題
——大学時代に特に力を入れたことは何ですか?
大きくふたつあります。ひとつ目はイギリスのセントラル・ランカシャー大学への交換留学です。私の所属していた学科は学生の「留学したい!」という思いにとても前向きで、手を挙げれば挑戦を全力で応援してくれる環境がありました。その姿勢は飯塚高校に近いかもしれません。
学費が私立としては比較的安価で、その分、交換留学の費用負担が少なく済む点も魅力でした。英語力を高めたい学生へのサポートも手厚く、必要なスコアをクリアすればスムーズに留学できる制度が整っていたのも心強かったです。思い切って1年間の留学に挑戦し、言語としての英語だけでなく、異文化の中で自分の考えを表現し、行動する力を培うことができました。
もうひとつ力を入れていたのが、中学校と高校の英語教員免許を取得するための教職課程の履修です。中学時代から漠然と「将来は英語の先生になりたい」という思いがありました。
ただ、教職課程は想像以上にハードで、通常の授業に加えて「英語学」「英語文学」「英語コミュニケーション」「異文化理解」など、英語教育の基礎から実践までを網羅する数多くの科目を履修する必要がありました。学びを通して「自分がどんな英語教師を目指したいのか」を真剣に考えるようになり、この経験が後の教育実習や大学院での学びへとつながっていきました。
——教育実習で印象に残っていることを教えてください。
中学校で教育実習を行った際に最も衝撃を受けたのは、自分が中学生だった頃と英語の授業内容がほとんど変わっていなかったことでした。グローバル化が進み、社会では「英語を使う力」が求められているのに、「このままでいいのだろうか」と強い違和感を覚えました。
一方で、自分が英語を話すことで、生徒の反応が目に見えて変わったことも印象的でした。
実際に英語を話せる先生はまだ少ない現状の中で、英語を使ってやりとりすると、生徒たちが一気に引き込まれていくのが分かりました。英語を使って伝える力が、生徒の意欲を引き出す大きなきっかけになる――そのことを肌で感じた経験でした。
また、大学で学んだ教育理論をそのまま現場に持ち込んでも、必ずしも思い通りにいくわけではないことも痛感しました。理想と現実のギャップに直面する中で、「もっと英語教育そのものを深く学びたい」「よりよい教え方を探りたい」という思いが強まりました。この経験が、教育学を専門的に学べるシェフィールド大学大学院への進学を決断する大きなきっかけになったと思います。

社会の変化に向き合う、教育学の最前線
——大学院での学びについて教えてください。どんな授業をとっていますか?
現在、シェフィールド大学大学院で教育学の修士課程に在籍しています。まだ入学して1か月半ほどですが、その中でも印象に残っているのが、社会的公正(ソーシャルジャスティス)と教育を結びつけて考える必修科目です。
この授業では、宗教・人種・移民といったテーマを通して、「変化する社会の中で教育はどうあるべきか」「どんな価値観を育むべきか」を問い直します。やや哲学的で難解な部分もありますが、日本ではあまり扱われないテーマだからこそ、新鮮で刺激的です。
イギリスでは、移民の増加や宗教的背景の多様化など、社会的課題が教育と密接に結びついていて、その現実を題材に学びます。日本でも今後、外国人労働者の受け入れ拡大などにより、同様の課題が生じる可能性が高いことから、これからの教育に必ず必要になる視点だと感じています。授業を通して「社会の変化に対応できる教育とは何か」を考える重要性を実感しています。
また、イギリスや欧米諸国は文化的にも日本より20〜30年先を歩んでいる印象があり、授業を受けながら「未来の日本の教育の姿を見ているようだ」と思うこともあります。難しさを感じつつも、確実に視野が広がっているのを感じます。
また、選択科目では言語習得について学んでいます。どんな生徒にどんな方法で言語を教えるか、どんなアクティビティが効果的かなどを、さまざまな国の学生と議論しています。異なる教育観や文化背景を持つ仲間と意見を交わすことで、自分の考えをより深く磨くことができています。

——授業の形式についても知りたいです。座学だけではなく、グループワークも多いイメージがあります。
学びのスタイルは日本とは大きく異なります。レクチャー(講義)で基礎的な内容を学んだ翌日には、少人数で行われるセミナー(グループディスカッション)で意見交換を行うという流れです。レクチャーは約2時間、セミナーは1時間ほどと授業時間自体は短いものの、次回の講義に向けて膨大なリーディング課題が出されるため、自主学習が学びの中心になります。
イギリスでは「インディペンデント・スタディ(自律学習)」の文化が根づいていて、自らの関心を軸に主体的に深掘りしていく姿勢が重視されています。その環境の中で、学ぶ内容を自分のものにする力が自然と培われていくのを感じます。
——卒業後の進路についてもお聞かせください。博士課程に進む予定はありますか?
今のところ、博士課程に進む予定はありません。大学院での学びを通して、教育や言語についてじっくりと考える時間を得られているので、次は実際の現場でその学びを生かしていきたいと考えています。
具体的な進路はまだ模索中ですが、英語を教える学校の先生になることも、教育や語学に関連する仕事に携わることも視野に入れています。
「絶対にこれをやりたい」と決めているわけではありませんが、どの道に進んでも、自分がこれまで学んできた英語や教育の知識を人の役に立てたいという気持ちは変わりません。
——ここまで大学院での学びについて伺ってきましたが、現地での生活についても教えてください。どんな暮らしをしていますか?
学生寮に入る選択肢もありましたが、大学時代の留学で寮生活を経験していたので、今回はひとり暮らしをしてみようと思いました。現在は「フラット(flat/ワンフロア型の集合住宅の一室)」と呼ばれるワンルームのアパートで暮らしています。
授業のない日は、近くのマーケットをのぞいたり、屋台で食べ歩きを楽しんだりと、イギリスならではの街の雰囲気や文化に触れる時間を大切にしています。

飯塚高校で育まれた「自ら学び、行動する力」
——ここからは過去の話を振り返っていただきます。飯塚高校を選んだ理由を教えてください。
兄が飯塚高校の野球部だったので、もともと飯塚高校のことは知っていました。高校選びの時期には、いくつかの学校のオープンキャンパスに参加していましたが、私立高校の多くは留学制度があっても費用が高く、「これでは現実的ではないかもしれない」と感じるプランも少なくありませんでした。一方、公立高校にも交換留学の仕組みはありましたが、帰国後に卒業が遅れてしまうケースもあると知り、どちらの選択肢にも迷いがありました。
兄がすでに通っていた安心感もあり、「オープンキャンパスだけでも行ってみよう」と足を運んだのが最初でしたが、説明を聞くうちに「ここで学びたい」と思えたのが飯塚高校でした。留学の機会があり、実費は交通費と渡航費程度で参加できると聞き、「ここなら留学のチャンスがある」と心が動いたんです。
さらに、ホームステイ制度が整っていて、現地の家庭に滞在できる点にも強く惹かれました。留学先は現地の公立高校で、現地の生徒と同じ授業を受けながら学べるというのも大きな魅力でした。
多くの私立高校では学生寮での滞在が一般的ですが、飯塚高校のプログラムではホストファミリーの家に滞在できるため、家族との会話や食事を通して自然な英語と文化に触れられるのが特長です。高校生のうちに、そうしたリアルな日常英語を体験できる環境は何より貴重だと感じました。
——高校生活で特に印象に残っていることは何ですか?
2年生のときにニュージーランドへ3か月間の留学をし、さらにベトナムでの短期文化交流にも参加しました。どちらも費用が抑えられていて、現地の家庭でホームステイしながら生活できたことは、今の留学生活にも大いに役立っています。部活動はグローバル研究部に所属し、ネイティブの先生や留学生と日常的に交流する中で、教科書では学べない生きた英語を身につけることができました。
私が所属していた特進コース(特進I類)はクラスの人数が少なく、先生との距離がとても近い環境でした。どの教科の先生も一人ひとりを丁寧に見てくれて、質問に行っても嫌な顔ひとつせず、納得いくまで付き合ってくださったのを覚えています。
私は中でも英語の先生方と関わる機会が多く、どの先生も教えることにとても熱心でした。受験対策では夜遅くまで指導してくださったり、プレゼンテーションの練習では発音や表現の細かい部分まで丁寧にアドバイスしてくれたりと、常に支えてもらっていたことを今でもよく覚えています。「やる気のある生徒には全力で応えてくれる」――そんな先生方に囲まれた環境だったからこそ、安心して挑戦できたと思います。
——飯塚高校での経験は今にどのように生きていますか?
学ぶことに前向きでいられる姿勢、周囲のサポートを素直に受け入れる柔軟さは、飯塚高校で育まれたものです。私は勉強が得意な方ではなかったですが、やりたいことがあれば全力で取り組む性格です。
そんな私を励まし、支えてくれた先生方の存在が、今の自分をつくってくれたと思います。
飯塚高校は、やりたいことが決まっている生徒にとって最高の環境です。先生方が本気でサポートしてくれるので、かつての私のように「英語を学びたい」「留学したい」という思いがある人にはぴったりの学校だと思います。
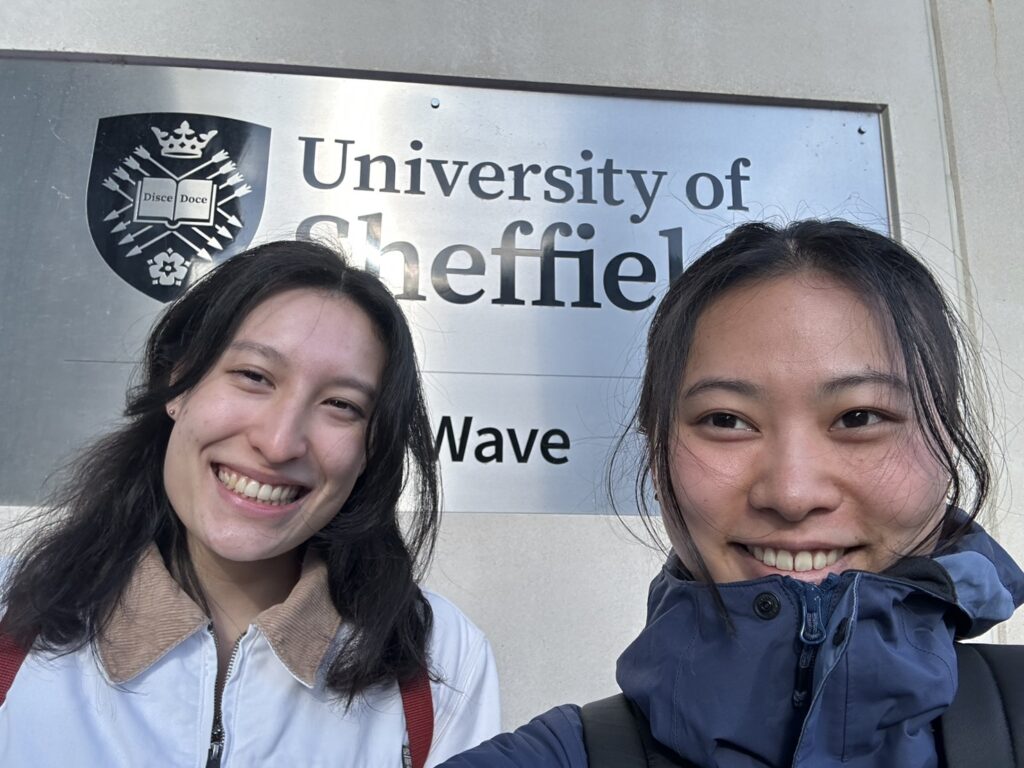
——「これを極めたい」という分野があり、そこに向かって一生懸命な生徒を全力でサポートしてくれる環境があることが伝わります。最後に、飯塚高校に興味のある中学生や保護者の方に向けて、メッセージをお願いします。
飯塚高校は「自分がやりたいこと」を持っている人にとって、とてもよい環境だと思います。「これをがんばりたい」と決めた生徒に対して、先生方が本気でサポートしてくれる学校です。
勉強はもちろん、部活動に力を入れたい人にも設備や環境が整っていて、自分の目的に合わせて全力で取り組むことができます。やりたいことがある人も、まだ模索中の人も、それを伸ばせる・見つけられる場所が飯塚高校だと思います。
——素敵なお話をありがとうございました!
今後も合格者インタビューを不定期で掲載していきますので、どうぞお楽しみに。
※記事内容は取材当時(2025年10月)のものです。
※コース名などは在学当時のものです。
※大学生活・留学生活に関する写真は山本さんよりご提供いただきました。
▶「探究プロジェクト(特進コース)」について詳しくはこちらを参照ください。


