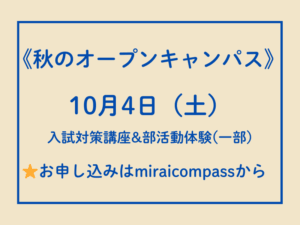Global・Local・Individualを育むDIY教育の力【飯塚高校×グッデイ 連携記念対談 後編】

飯塚高校とホームセンター「グッデイ」がタッグを組み、学校と地域の企業や人々がコラボレーションする新しい取り組みが動き始めました。「DIYによる教育連携および地域貢献活動に関する協定書」締結を記念して、グッデイ代表取締役社長の柳瀬隆志さんと本校 常務理事/校長補佐・嶋田吉朗(以下、敬称略)による対談が実現。
前編では、その出会いの背景や商店街との関わり、地域資源を生かす発想についてお届けしました。後編では、最初に手がけたプロジェクトである寮のリノベーションから始まった「DIY教育」に焦点を当てます。DIYと教育の親和性、そして学校から地域へと広がる活動の可能性をおふたりが語ります。
プロフィール
柳瀬 隆志(やなせ たかし)
東京大学経済学部卒業後、2000年に三井物産入社。2008年より家業である嘉穂無線(現グッデイ)に入社。営業本部長・副社長を経て2016年、嘉穂無線ホールディングス及びグッデイ代表取締役社長に就任。ゼロから組織のDX化を主導し、2022年6月に開催された第1回「日本DX大賞」の「大規模法人部門」にて初代DX大賞を受賞。著書『なぜ九州のホームセンターが国内有数のDX企業になれたか』(ダイヤモンド社、2022年、酒井真弓氏との共著)は大きな話題に。
嶋田 吉朗(しまだ きちろう)
学校法人嶋田学園常務理事、飯塚高等学校校長補佐。ICT・グローバル教育・地域連携・大学連携等を統括。「ヲソラホンマチ」を中心に飯塚市の旧市街活性化に従事し、本校の「街なか学園祭」を主導。社会学者としても活動し、関西大学客員教授および経済・社会研究所非常勤研究員。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。主著に『地方経済人の結社と市民社会』(大学教育出版、2023年、日本NPO学会賞奨励賞を受賞)。
寮のリノベーションから始まったDIY教育

柳瀬:飯塚高校とのコラボレーション第1弾(★)は、2025年6月に行った愛宕寮313号室の壁の塗装と床の張り替えでした。サッカー部や野球部などの強化部に所属する生徒(希望者)が入寮する建物での取り組みです。当初は全社を巻き込むようなプロジェクトになるとは思っていませんでしたね。
★寮のリノベーションについては、本対談企画コラボ記事「自分たちの手で、寮を変える」──飯塚高校サッカー部とグッデイが挑んだDIYリノベーションプロジェクト (グッデイnote)に詳しく紹介されています。ぜひお読みください。
嶋田:きっかけは、寮管理スタッフから「壁に空いた穴を修繕したいが費用が高い」と相談を受けたことでした。そこで「それならグッデイに相談してみましょう」と提案したのです。グッデイが手がけてきた団地再生などのDIY実績(※)を伝えると、スタッフも驚きながら興味を示してくれました。
※空き家問題の解決とリノベーションへの関心の高まりを背景に、築50年以上の福岡市東区名島団地で実施された「グッデイ団地プロジェクト」が一例。福岡県住宅供給公社とグッデイが連携し、団地の魅力を再発見するとともに、現代のライフスタイルに合った暮らし方を提案している。初回の取り組みでは、秋のスタートから数ヶ月で個性あふれるリノベーションルームが完成した。2024年3月にプレスリリースが出ている。

柳瀬:話を聞いて「それなら本格的にやりましょう!」と決定し、6月中旬から下旬にかけて4日間、各日7時間かけて作業しました。7月3日にはお披露目会も開催しました。生徒たちの反応はいかがでしたか?
【関連記事】飯塚高校 愛宕寮 DIY改修第一弾をお披露目~グッデイとの共創プロジェクト~
嶋田:最初はDIYの完成形が想像できない生徒もいましたが、実際にやってみると大半が「楽しい」と感じたようです。家族がDIY好きで「自宅でもやってみたい」と話す生徒や、メディア取材をきっかけに「自分の個室もDIYしたい」と希望する生徒も出てきました。
柳瀬:次はクラウドファンディングを組み合わるのも面白いですね。「生徒がゼロから自分の部屋をつくるので応援してください」と発信すれば、主体性がより引き出されますし、外部の方にも魅力的な企画に映るはずです。
嶋田:確かに。とても可能性のある取り組みだと思います。改めてご相談させてください!
柳瀬:もちろんです。もうひとつ伺いたいのですが、DIYは一見すると授業と直接関係がない活動です。それを教育に結びつけようとされた嶋田常務の発想が本当に素晴らしいと感じています。DIYを教育に取り入れることにした背景をぜひ教えてください。
嶋田:今の教育では主体性や探究学習が重視されています。先行きが見えない時代だからこそ、自分の意思で考え、創造的に行動する力が求められるのです。飯塚高校は「GLI(Global・Local・Individual)」を教育目標に掲げていますが、DIYはその理念にぴったり合致しています。
地域の企業や人々とつながるローカル性、世界的潮流であるDIYのグローバル性、そして自分の部屋づくりを通じて一人ひとりが「どうしたいか」や手段を自ら考え、個性を発揮できること。DIYにはGLIのすべてが含まれているんです。
柳瀬:とても共感します。今のお話を伺って、グッデイで働き始めた頃のことを思い出しました。実家がホームセンターを経営していたにもかかわらず、私自身はDIY経験がほとんどありませんでした。ところが、入社後、社員から暮らしに役立つ知恵や技術を教わり、日常生活で大いに役立つことを実感しました。
DIYは学校ではほとんど教わらず、誰かに体系的に習う機会も少ない分野ですが、この仕事を通じて自然に身につき、暮らしを豊かにする知識になるなと気づきました。店舗で得た学びは非常に大きく、今の時代こうしたことを教わる場が少ないことを強く感じます。小学校で野菜を植えるといった経験はあっても、生活に直結するより実用的な知識や技術は、もっと時間をとって教わる機会が必要だと思います。
嶋田:私も同じ思いです。大学時代にドイツへ留学した際、学生たちが自分の部屋を自由にカスタマイズしている姿を見て大きな衝撃を受けました。その光景がとても印象に残っていて、DIYは自分の暮らしを自分でつくる営みであり、それが教育にも通じると確信しています。そして、私たちの教育方針に合う学びだと感じています。
学校内から地域へ、DIY教育の知見を広げていく
柳瀬:教育の現場でこうしてお話を聞いていただけるのは本当にありがたいことです。私たちは以前からこのような取り組みを望んでいましたが、どこに相談すればよいのか分からない状況が続いていました。今回、嶋田常務からお声がけいただき、双方の思いが一致してチャレンジングなプロジェクトに発展できたことをとてもうれしく思っています。
先日、母校の小学校で校長先生方と座談会を行ったのですが、「自分たちが教えていることが社会でどう役立つのかが見えにくい」という課題を抱えていると伺いました。だからこそ、教育現場ではさまざまな分野で活躍する人の話を聞き、教育のヒントを得たいという思いをお持ちのようです。
これからの時代、計算や文章作成といった作業はAIが担うようになります。では人間は何をすべきか。その答えのひとつは、ものづくりや創造性といったAIでは代替できない領域だと私は考えています。その意味でも、飯塚高校さんの教育目標と私たちの方向性は非常にうまく重なっていると感じます。

ただ何より大事なのは、生徒たちが「楽しい」と感じられるかどうかです。楽しければ自然と続き、深い学びにつながります。今回の取り組みはテレビをはじめとしたメディアにも多数取材いただきましたが、その映像で拝見した生徒さんたちは、とても楽しそうに黙々と作業していましたし、「DIYを仕事にしたい」という声まで出ていました。このプロジェクトが将来の選択肢を広げるきっかけになれば、これほどうれしいことはありません。
こうした教育連携はほかにあまり例のない取り組みですが、飯塚高校がこれまで進めてきた「街なか学園祭」などの地域活動とも通じる部分があります。今回のDIYをきっかけに、地域との関わりはどのように広がっていくとお考えですか。
嶋田:最初は寮のモデルルームづくりから始まりましたが、すでに「自分の部屋でもやってみたい」という声が多く、今後は寮全体や生活の場を自分たちでより良くしていく取り組みへ広げたいと考えています。最終的には、生徒一人ひとりが理想の部屋を実現できる環境を整えることが目標です。
さらに今回学んだDIYの技術は、商店街の活性化にも応用できると考えています。シルバー人材センターの皆さんをはじめ地域の方々と協力し、空き家や空き店舗の問題解決に役立てたい。過去には、生徒が学園祭で使用するために整備した空き店舗に新しいテナントが入った例もありました。こうした活動を継続すれば、町全体に良い循環が生まれるはずです。
柳瀬:素晴らしいですね。私自身も、飯塚市の商店街に何らかの形で貢献できないかと考えてきました。かつては多くの店で賑わった通りも、今では空き店舗が目立っています。しかし、この場所自体は大きな資産であり、まだまだ生かせる可能性があります。
私はこれまで団地や古民家の活用に携わってきましたが、商店街も同じように工夫次第で魅力的な場に生まれ変わります。立地の強みがある飯塚だからこそ、民間レベルで実績を積み上げ、運営や連携を進めたい。たとえ小さな取り組みでも確かな成果を出すことが、活動の面白さにもつながると考えています。
地域活性化とは「アップデート」だと思います。場所や人が変わらなくても、更新されなければ古びてしまう。逆に少し手を入れるだけで、同じ場所でも活気が生まれ、人が集まります。日本ではゼロから新しいものをつくる発想に偏りがちですが、既存の場所をリノベーションやDIYでアップデートする方法は、もっと広がってよいはずです。
そして何より、この商店街には「人の力」という資源があります。とくにシニア世代の経験や知識は大きな強みですし、それに若者の感性が加われば、人材不足が叫ばれる中でも力強いチームをつくることができます。当社が掲げる「社会課題の解決を事業にする」という方針も、まさにこうした取り組みと重なり、良い実践例になるのではないかと感じています。
さらに言えば、地域資源を最大限に生かすには、若い世代や教育機関が主体的に関わることが欠かせません。その点で、飯塚高校が街中に拠点を持ち、日常的に地域とつながっていることは大きな強みだと思います。
「街なかに活動拠点を持つ」大きな強み

嶋田:おっしゃる通りで、私たちの学校がこのプロジェクトにうまく取り組めている理由のひとつは、街中に拠点を構えていることです。シルバー人材センターのすぐ近くに、ヲソラホンマチというイベント広場のような施設を所有しています。
「街なか学園祭」について話してほしいという依頼を受け、各地でお話しする機会があります。その際によくお伝えしているのは、公立学校では難しい場合もありますが、思い切って街中に活動拠点を持つことの価値です。
土地を基盤にしたつながりは非常に強いものです。私たちの学園のルーツは、広場に面した小さな建物の一角にあった職業教育の私塾にあり、現在はそこから移転しました。離れてしまえば関係は途切れがちですが、私たちはさまざまな事情から土地を介したつながりを維持しており、それが今回の取り組みにもつながっています。こうした「土地を媒介としたつながり」は、地方都市で新しい活動モデルを考える上で重要なヒントになると感じています。今回の事例もその好例になり得るでしょう。
柳瀬:地元への愛着こそが地域活性化の原動力ですね。そこに暮らしているからこそ「何か役に立ちたい」と思えるし、子どもの頃からの思い入れがあるからこそ行動につながる。昔の話を聞き合えば、世代を超えた会話も生まれますし、それは教育にも良い影響を与えるはずです。
嶋田:私たちの学園にはこども園(認定こども園 愛宕幼稚園)があり、0歳後半くらいのお子さんからお預かりしています。シルバー人材センターの皆さんにも可愛がっていただくなど、自然と多世代交流の場ができています。0歳から高校生までと、学園全体で幅広い世代が育っていて、高齢者や企業、大学との連携がさらに進めば、ますます面白い展開が生まれていくと思います。
柳瀬:子どもを預けたいと感じる学校ですね。学科の勉強だけでなく、地域と深くつながる教育をされている点が素晴らしい。生活の技術は学校教育で十分に教えられていない部分ですから、そういったことももっと広めてほしいです。
嶋田:大学側も、地域と連携する活動を評価する時代になってきています。この地域がそうした流れに遅れないよう、私たち大人側も積極的に取り組んでいく必要があります。
柳瀬:私たちの会社は、もともと社会貢献への関心が高い組織だと思います。嘉穂無線(※)創業者である祖父が無線の普及を目指して事業を起こしているので、そのDNAがあります。グループ会社のイーケイジャパンでは、学べる電子工作キット「エレキット」の開発・販売をしており、「教えることで喜んでもらう」感覚がずっと受け継がれています。これからも飯塚高校の活動を支援させていただきたいです。
※1950年創業。2007年に嘉穂無線が持株会社に移行し、嘉穂無線ホールディングスに商号変更した
嶋田:とても心強いお言葉です。こちらこそ、よろしくお願いいたします。

飯塚高校とグッデイの協働は、教育・地域・企業が同じ方向を向いたときに生まれる新しい価値を示しています。DIYを通じて育まれるのは、手を動かしてものづくりをする技術だけでなく、自ら考え行動する力、そして地域を愛する心。
生徒にとっては未来を切り拓く学びの機会であり、地域にとっては新たな活性化のモデルです。この挑戦は、中学生や保護者、地域企業にとっても「学びの未来」と「地域の未来」を同時に描く、ほかに類を見ない取り組みだといえるでしょう。
私たちのコラボレーションの様子は今後も随時発信していきますので、ご注目いただけるとうれしいです。
※記事内容は取材当時(2025年8月)のものです。