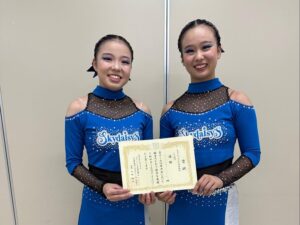生き抜く人ではなく「時代の変化をつくる人」を育むGLI教育【飯塚高校 教員対談】
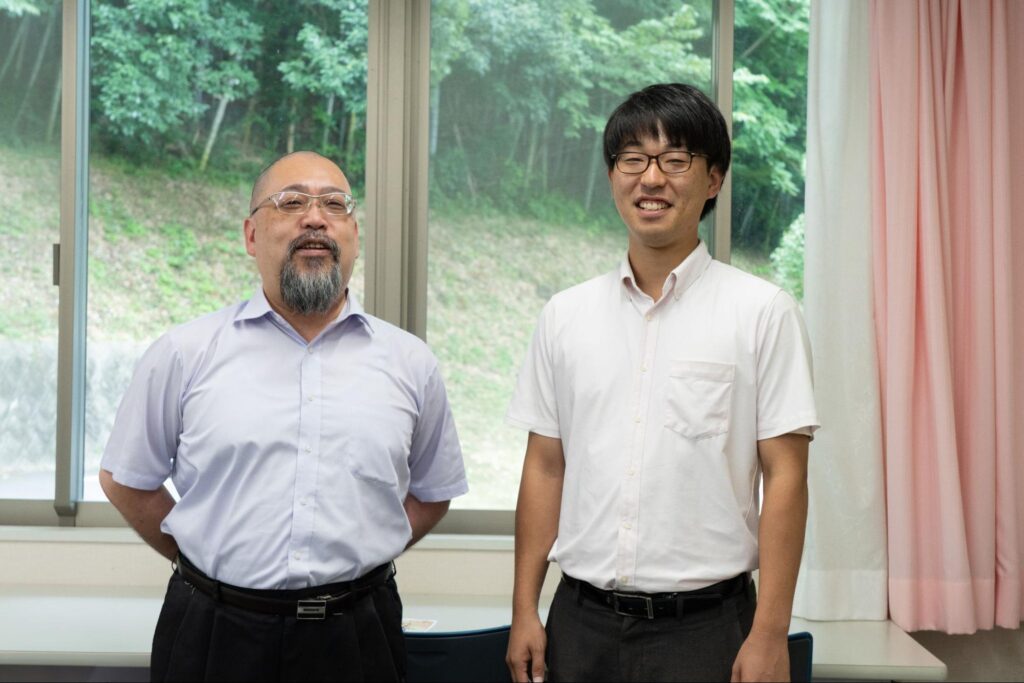
飯塚高校の教育理念「GLI(Global・Local・Individual)」は知識習得にとどまらず、社会とつながりながら主体的に学びを深め、自ら未来を切り拓く力を育むことを目指しています。その現場には、生徒とともに挑戦を重ね、学びの可能性を広げ続ける教員の姿があります。
数学を通して挑戦する姿勢を育てる堀之内翼先生。日常の対話を通じて内発的な動機を引き出す菊池祐介先生。ふたりは探究プロジェクト(特進コース)をはじめ、多様な学びの場で生徒の人格形成と進路形成を同時に支え、社会で通用する力を培ってきました。
今回、両教員による対談が実現。街なか学園祭やGLIプロジェクトといった実践の中で育まれる生徒の成長、そして自らも挑戦者であり続ける教員としての在り方が語られました。
(プロフィール)
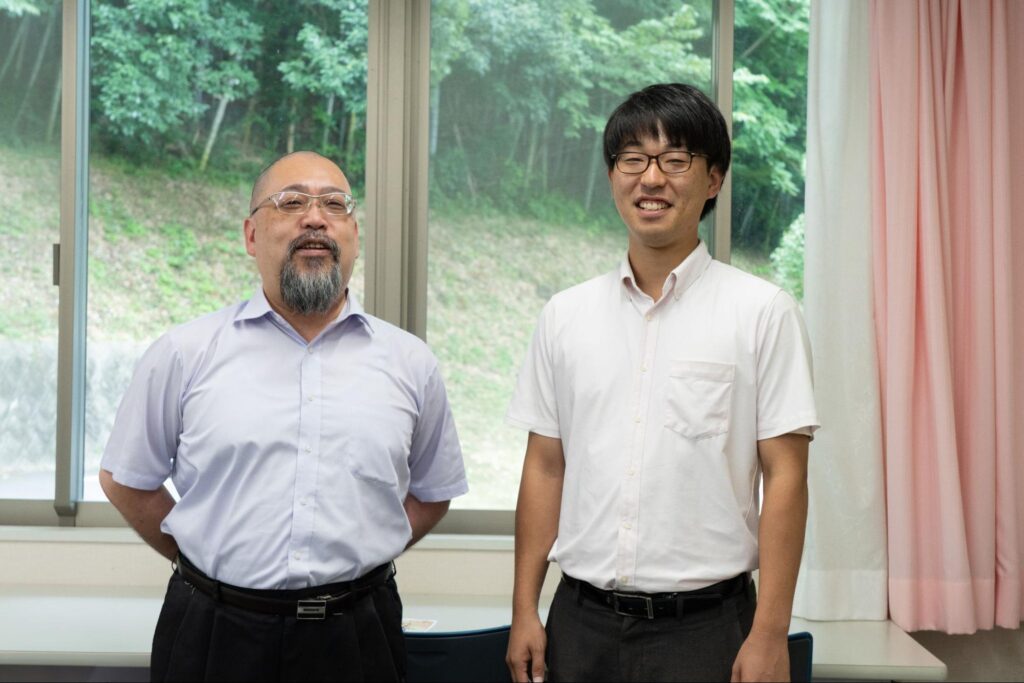
キャプション:左から菊池先生、堀之内先生
堀之内翼先生
数学担当。2018年に飯塚高校へ着任し、探究プロジェクトを担当。着任1年目から生徒会顧問を務め、体育祭や学園祭など学校行事を通じて生徒の主体性を育んできた。2021年の商店街連携協定を機に地域活動を推進し、2025年に「まちLabo」を立ち上げ発起人として指導。生徒が社会で通用する実践力を磨ける場づくりに挑戦している。
菊池祐介先生
国語担当。別府大学文学部国文学科で近現代文学を専攻。中学校教員を経て、魚屋勤務や大学・専門学校進学を目指す大人のための予備校運営、学習塾経営など多様なキャリアを経験。2019年に非常勤講師として飯塚高校に着任し、探究プロジェクトを中心に授業を担当。生徒の「本音のかけら」を日常の対話からすくい取り、内発的動機を引き出すよう努める。若手とベテランをつなぐ中堅教員として、生徒が社会で活躍する力を育む役割を担う。
個性を尊重し、挑戦を支える校風に惹かれて
——外部の教育現場で経験を重ね、飯塚高校に“外の風”を運ぶ立場として加わった菊池先生。外部の視点から見て、飯塚高校のどの点に魅力を感じ、ここで働こうと思われたのでしょうか。

菊池:最初のきっかけは、嶋田吉朗・常務理事/校長補佐との出会いです。2018年頃、わざわざ隣の田川市にある私の塾まで足を運んでくださり、対話を重ねるうちに「この魅力的なリーダーと働き、この方が描く未来を見たい」と強く思いました。その情熱に触れ、飯塚高校の可能性を感じたんです。
その根底には、GLIの理念につながる考え方がありました。教育は机上の学びだけではなく、経験を通して広がるもの。ベテランの先生方が培ってきた経験に支えられながら、若い先生たちが新しい挑戦に取り組める環境をつくること。その間をつなぐのが自分のような中堅教員の役割だと思っています。
トップが情熱的であれば、私たちも失敗を恐れず挑戦できる。街なか学園祭で若い先生方が次々と新しい試みに挑む姿を見て、この環境の大きな力を実感しました。GLIという教育理念ができる前から、個性を尊重し挑戦を支える文化は息づいていた——その風土こそ、私が飯塚高校に惹かれた理由です。
——堀之内先生は、外部から加わった菊池先生とともに仕事をするなかで、どのような影響や学びを受けてきましたか。第一印象の思い出や忘れられないエピソードがあれば教えてください。
堀之内:「国語の教科書をとてもいい声で読む先生だな」というのが第一印象でした。その後、私が担任を務めたクラスで国語を担当していただいたのですが、その際、生徒に関するたくさんの情報を共有してくださいました。私が担任になったのは3年次からでしたが、生徒たちはそれ以前から菊池先生と深く関わっていたようです。
特に印象に残っているのは、ある男子生徒の進路に関する出来事です。本人は「大学進学をしたい」と話しており、私もその方向でサポートしていました。しかし菊池先生との対話を通じて、「本当は医療・看護の道に進みたい」という本音を打ち明けてくれたのです。その後、保護者を交えた三者面談で進路を調整し、現在その生徒は希望する道を歩んでいます。
もし菊池先生がその本音を引き出していなければ、生徒が本当に望む進路へと導くことはできなかったかもしれません。生徒と真摯に向き合い、隠れた思いをすくい上げる姿勢から、私自身も大きな学びと影響を受けています。
対話で生徒の「本音のかけら」を引き出す
——菊池先生は、生徒が言葉にできずにいた思いにアプローチできた理由は何だと考えますか。普段のコミュニケーションでどのようなことを心がけているのでしょうか。
菊池:その瞬間ごとに生徒を一番に考えることが大切だと思います。言葉や態度、雰囲気、声のトーンなどから、奥にある言外の意味を感じ取るようにしています。子どもたちはすべてを語るわけではないので、その気づきを促すのが大人の役割だと考えています。
私は生徒と向き合うとき、「指導する」という感覚は持ちません。内発的動機を引き出し、自分のなかにある本当の気持ちに気づけるよう支えることを意識しています。大人としての厳しさを一定程度持って接しながらも、生徒の言葉を頭から否定することはしません。恥ずかしさや諦めから本音を隠す子が多いからこそ、「恥ずかしくない」「間違えてもいい」という安心感を与え、諦める前に小さな火を灯すよう心がけています。
真正面から向き合いながら、ときには引っ張り、ときには支えて背中を押す。そのバランスを柔軟に取りながら、生徒が自ら気づける環境を整えているつもりです。
そして何より大切にしているのは日常の何気ないおしゃべりです。授業や面談だけでなく、日頃のやりとりのなかにこそ、生徒の“本音のかけら”が潜んでいる。私はそのかけらを探すつもりで、常に耳を傾けています。堀之内先生は生徒の可能性や新たな一面を対話の中で引き出すために、どのような工夫をされていますか。

堀之内:本音のかけら、非常に参考になります。私は初回の授業で必ず生徒たちに伝えることがあります。それは「高校生活では必ず何かにチャレンジしてほしい」ということです。そして同時に、私自身も今なおチャレンジャーであることを伝えています。常に新しいことに挑み続ける存在でありたいと思いますし、生徒たちにも挑戦者としての思考や行動を示したいのです。
数学の授業は、中学校から苦手意識を抱えてハードルが高いと感じる生徒もいれば、逆に得意で物足りなさを感じる生徒もいます。だからこそ、まずは「得意ではない科目にも挑戦してみよう」という気持ちを持ってもらうことが大切だと考えています。そのために授業の冒頭では、自分自身の夢や現在挑戦していることを語り、みんなにとってはこの1年間、数学に取り組むことそのものをひとつのチャレンジとして、向き合ってみようと話しています。
内発的動機が自然と育まれる街なか学園祭
——本音を引き出す日々の対話と同じように、学校の外に開かれた活動からも多くの学びがあります。外部の視点から見たとき、街なか学園祭はどのように映りましたか。
菊池:街なか学園祭は、地域に与える影響が非常に大きいと感じます。3,000人を超える人々が集まる光景は、私の好きなプロレスの興行を思い起こすほどの規模感です。その人数が飯塚に集まること自体が驚きですし、しかもプロのイベントスタッフではなく、生徒が主体となって運営し、先生方がそれを支えている。これは大きな価値があります。
塾生を連れて訪れた際には、「これを学校がやっているの?」と皆一様に驚いていました。外部の目から見ても、学校がここまで地域と深く関わりながら大規模なイベントを形にしているのは素晴らしいことだと思います。

堀之内:ありがたいですし、とても誇らしいですね。街なか学園祭は、生徒にとってはビジネスやクラス企画を経験し、学びにつなげる場であると同時に、地域の方々に飯塚高校の取り組みを直接知っていただける大切な機会です。
毎年、校内でオープンキャンパスを行っていますが、私にとって本当の意味での最大のオープンキャンパスは学園祭だと思っています。通常のオープンキャンパスは中学3年生が対象ですが、学園祭は幼稚園や保育園に通う子どもたちや小学生も参加でき、地域全体が飯塚高校を体感できる一大イベントです。
今日、隣の田川市から塾の生徒さんを連れてきていただいていると伺い、本当に感激しましたし、「やってきてよかった」と改めて思いました。
——先生方が担当されている探究プロジェクトの生徒たちは、難関大学を目指して学業に励む一方で、街なか学園祭のように地域に飛び出して学ぶ活動にも積極的に参加しています。机上の学びと地域での学びを両立させている姿がとても印象的です。
菊池:受験対策に力を入れ、勉強一本で進む学校も少なくありませんが、飯塚高校では内発的なものをとても大切にしています。今取り組んでいる勉強が社会とどうつながるのかを、実体験を通して体感できることが大きな特徴です。
学園祭では、自分たちで企画して販売を行うだけでなく、シルバー人材センターの方をはじめ地域のさまざまな方々が関わり、応援してくださっていることに気づく生徒もいます。そこで「応援されるだけでなく、自分たちも何かを返したい」という思いが芽生え、地域に貢献したいという意識へとつながっていきます。
点数を追うことが目的ではなく、「その先」にある社会とどう関わるかを示してくれるのが街なか学園祭です。だからこそ生徒たちは「これについて勉強しよう」「この力を身につけたい」と自ら考え、行動できるようになる。実際、街なか学園祭を通じて夢や進路を見つけた探究プロジェクトの生徒は、昨年だけでも何人もいました。
時代の遥か先を走っていた飯塚高校のこれまでとこれから
——具体的な事例を教えてください。
菊池:サッカー一筋だった生徒が、商店街活性化の活動に関わったことをきっかけに、「盛り上がりを一過性で終わらせず、継続性をどう持たせるか」を自らのテーマに据え、大学で経済学を学ぶ道を選びました。学園祭を通じて新しい世界に触れ、将来の夢を見出したのです。学園祭は一行事にとどまらず、生徒が自分の課題や関心を発見し、夢実現へ向けた行動へとつなげる場になっています。
——学園祭を通じて生徒たちは、普段の学校生活だけでは得られない広い視野を持ち、ここでしかできない経験を重ね、一般的な高校生とは異なる次元の学びをしているように感じます。

堀之内:2022年に初めて街なか学園祭を開催した当初は、創立60周年の記念イベント的な意味合いが強く、「自分たちで楽しみながらつくろう」という雰囲気でした。けれど回を重ねるごとに、そこに学びの要素が加わっていきました。シャッターが閉まった商店街を見て「ここでビジネスをやりたい」と語る生徒もいれば、昨年の生徒会長は廃棄野菜を活用したビジネスを企画し、実際に形にしていました。
こうした経験は大学入試にも直結していて、総合型選抜や推薦入試で提出する志望理由書の質は確実に高く、深くなっています。地域の課題に触れ、行動へと移す過程で、生徒たちは自分の進みたい道をより鮮明に描けるようになっているのです。
菊池:一方で、課題として感じているのは、活動の価値をどこまで社会に伝えられるかという点です。というのも、取り組んでいる我々教員と高校生自身に「高校の学園祭ならこのくらいで十分だろう」と自分にリミッターをかけてしまっていると、本来の良さが外に伝わりにくいからです。私たちの挑戦にはもっと大きな価値がある。だからこそ、その枠を外し、全力でやり切ることで、地域や社会の方々にも一層強く魅力が伝わるはずだと思います。
飯塚高校は、文科省が近年掲げる「個別最適化」のような教育を、すでに何十年も前から当たり前のように実践してきました。時代がようやく追いついた今、高校の枠を超え、大人になる手前の生徒を支える場として、さらに新しい挑戦へと踏み出すときかもしれません。
「時代の変化をつくる人」を輩出し続ける学校へ
——飯塚高校はこれまでも時代を先取りし、さまざまな挑戦を積み重ねてきました。その流れのなかで、2025年は春以降「GLIプロジェクト」が次々と動き出しました。こうしたスピード感ある挑戦を、先生方はどのように受け止めていますか。

堀之内:学校企画部の立場から振り返ると、今年はまさに「変化を形にする年」だったと感じます。メイクアップデイやフリーファッションウィークなど、新しい試みを次々に実現できたのは、これまで飯塚高校が築いてきた確かな土台があるからです。変化は必要不可欠であり、私たち教員もその歩調に合わせるために本気で向き合っています。
生徒たちは日頃から多様な情報や価値観に触れているため、変化に対する適応力が非常に高い。自分の頭で考え、ルールやマナーを踏まえながら表現する力を、この機会にさらに伸ばしています。新しい取り組みが始まっても、戸惑うより「どう生かすか」に意識が向いている——そんな前向きさを強く実感しています。
菊池:クラスの生徒を見ていると、「大人がやっと自分たちを信頼してくれた」——そんな受け止め方をしているように感じます。「明日は好きな格好で登校していい、明後日はこれまで通りのルールに戻す。君たちは切り替えができると信じている」と伝えると、生徒はその期待に応えてくれる。フリーファッションウィークで自由に自己表現した生徒たちも、イベントが終われば自然と普段の姿に戻っていきます。
大人の側には「指導しないと不安」という感覚が残りやすいかもしれません。しかし今の生徒は学校の外の人や情報にも触れており、視野も知識も広い。だからこそ、これからの教育で大切なのは「自分を律する心」を育むサポートをすることだと思います。それが身につけば、学びは自ずと前に進んでいくのです。
——今のお話にもあったように、学びが自然と前へ進んでいく仕組みは、探究プロジェクトをはじめとする飯塚高校の大きな特徴だと思います。各コースでは、どのような取り組みを展開しているのでしょうか。
堀之内:私の印象では「外に出て学ぶ」活動が、ここ数年でますます増えてきています。グローバルコースでは海外の協定校との交流、探究実践コースでは大学や企業とのコラボレーションが進んでいます。最近では、筑豊の青果市場から提供された野菜を題材に学び、その後実際に販売まで行うという取り組みもありました。
教室で座って学ぶだけではなく、体験を通じて学ぶ方向へと確実にシフトしています。体験学習は講義よりも記憶定着率が高いとラーニングピラミッドでも示されています。アカデミック、グローバル、探究実践、医療教育——どのコースも「動いて学ぶ」を根底に据えたカリキュラム設計になっていると感じます。
菊池:校訓である「熱・力・誠」(熱い心をもって真摯に学び、努力を継続することで真の力を身に付け、何事にも誠心誠意、誠の心を尽くす)は、飯塚高校における人格形成の揺るぎない土台です。その伝統があるからこそ、いま私たちは教育理念GLIを“生き方”の学びとして重ねることができる。新しいものは過去を否定して生まれるのではなく、積み重ねの上にこそ育つものだと考えています。
グローバルであり、ローカルを大切にし、インディビジュアル=自分らしさを発揮する——GLIは、大学進学や就職“のため”に学ぶのではなく、変化の時代を自分ごととして切り拓く生き方の指針です。私たちは、変化の波に流されるのではなく、変化を生み出す主体として踏み出す力を育てたい。AI時代にあっても「使いこなす側」として成長できるよう、学校の枠を超え、社会に開かれた学びを設計しています。
今、飯塚高校が確かな歩みを進められているのは、長年にわたり伝統を築いてきた先生方や先輩方の存在があってこそ。その基盤の上にGLIを重ね、特進をはじめとする各コースで「学んで・動いて・体感する」学びを実現し、「変化をつくる人」を輩出する教育が形づくられています。
教員もチャレンジャーとして、学びの進化を止めない
——最後に、今後の展望、やりたいことを教えてください。

堀之内:やりたいこと、仕掛けていることは数えきれないほどあります。まず、体験や校外活動をさらに広げると同時に、学校である以上「学びの核」である勉強そのものもアップデートしたいと考えています。その一環として、大学の理学部時代の仲間と数学のゲームを開発するプロジェクトを進めています。数学に苦手意識を持つ生徒にとっても、楽しさから学びに入れる“入口”を広げたいのです。
さらに、農業×テクノロジー(ドローンなど)にも挑戦するつもりです。地域の一次産業と現代の技術を結びつけ、教室での学びをリアルな課題解決へと直結させたい。生徒が「動いて学ぶ」機会を、より立体的に増やしていきたいと考えています。
生徒が主体的に地域と関わるプロジェクト「まちLabo」は、イベント運営や商品販売を通じて“実際のビジネスの流れ”を学び、その収益を地域に還元していく——教育と社会貢献の両輪で走る組織です。こちらは学校内ベンチャーのような存在に育てていくつもりです。
教員としての責任を果たしながら、自らも挑戦者として前に立つことで、新しい学びの場を切り拓いていきます。
菊池:これからの学びで最も大切にしたいのは、自ら問いを立てる力です。自分の問いを起点に、実践し、振り返り、さらに問い直す——そのサイクルを日常化していきたいと考えています。あわせて、教科の垣根を越える学びを推進していきたい。国語だから国語、数学だから数学といった枠内に収まるのではなく、学びを横断させたいのです。
たとえば、国語の授業で数学的な視点に触れる、数学の学びを社会課題に結びつける、といったつながりです。もちろん、土台となる基礎知識の定着は欠かせません。そのうえで教科を超えた「学問」へと開かれた授業づくりを目指しています。生徒一人ひとりが、自分の問いを携えて教科を横断し、世界にはたらきかける力を育むこと——それが私の描く未来です。
——本日は貴重なお話をありがとうございました!
今回の対談を通じて浮かび上がったのは、飯塚高校が大切にしている「伝統の上に挑戦を積み重ねる教育」の姿です。
校訓「熱・力・誠」による人格形成を土台に、教育理念GLIを重ね合わせることで、生徒たちは知性・主体性・社会性を兼ね備えた学びを実現しています。
街なか学園祭やGLIプロジェクトに代表される取り組みは、一行事にとどまらず、学力と社会をつなぐ実践的な学びの場。ここでの経験が、生徒たちが未来を切り拓く力を確実に育んでいます。
そして堀之内先生と菊池先生の言葉から伝わってきたのは、教員自身もまた学びを止めず、挑戦を重ねる先導者であるということ。飯塚高校はこれからも、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、「変化をつくる人」を輩出し続けていきます。
※記事内容は取材当時(2025年8月)のものです。